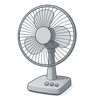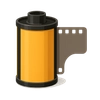話す電線の夢
こんにちは。私の名前はアレクサンダー・グラハム・ベルです。私は少年時代から、音というものにすっかり魅了されていました。というのも、私の愛する母と素晴らしい妻のメーベルは、耳が聞こえなかったのです。私は、二人に私の声を聞かせる方法を見つけたいと心から願っていました。この願いが、私の研究の原動力となったのです。ボストンにある私の作業場は、電線や電池、奇妙な形をした装置でいつもごった返していました。そこで、私の優秀な助手であるトーマス・ワトソン君と一緒に、昼も夜も研究に明け暮れていました。私たちは、電信のようにカチカチという音やブザー音を送ろうとしていたのではありません。もっとずっと大きな夢があったのです。私たちは、本物の人間の声を電線を通して送りたかったのです。何マイルも離れた場所にいる人と、まるで同じ部屋にいるかのように話せるなんて、想像できますか。それが私たちの目標であり、壮大な実験でした。それはとても難しいパズルで、多くの人々には不可能だと思われていましたが、私たちは必ず解き明かしてみせると固く決心していました。
すべてが変わったその日は、1876年3月10日のことでした。研究室の空気は、興奮と少しばかりの緊張感で張り詰めているように感じられました。私たちは新しい送話機に何週間も取り組んできて、これまで以上に成功に近づいていると感じていたのです。私は送話機のある部屋に、そしてワトソン君は別の部屋で受話器のそばで待機していました。私たちは何度も何度も試みましたが、聞こえてくるのはパチパチという雑音か、あるいは何も聞こえないかのどちらかでした。いらだちは募るばかりでした。私が装置のネジを慎重に調整していたその時、手が滑ってしまったのです。「しまった!」と思った瞬間、電池の酸が入った瓶が倒れ、ズボンに染みてヒリヒリする液体がこぼれてしまいました。火傷のようでした。私は考える間もなく、送話機の送話口に向かって叫びました。「ワトソン君、こっちへ来てくれ!君に会いたい!」。メッセージを送ろうとしたわけではありません。ただ助けを求めて叫んだだけでした。一瞬、静寂が訪れました。足はヒリヒリと痛み、自分の不器用さに少しばかばかしく感じました。本当に電線を通して何かが伝わったのだろうか。その時、廊下を急いでくる足音が聞こえました。ドアが勢いよく開き、そこにワトソン君が立っていました。彼の目は驚きで見開かれていました。「ベルさん!」と彼は興奮で震える声で叫びました。「聞こえましたよ。すべてはっきりと聞こえました!」。私たちは顔を見合わせ、ゆっくりと笑みが広がっていきました。やったんだ。私たちは本当にやり遂げたのです。私たちは飛び上がって、喜びのあまり笑い、叫びました。人間の声が、電線を旅した瞬間でした。
あの偶然の叫びは、単なる助けを求める声以上のものになりました。それは、電話の誕生でした。その瞬間、私は世界が二度と同じ姿ではいられないだろうと悟りました。遠く離れた愛する人からの知らせを聞くために、何週間も手紙を待つ必要はもうありません。家族も、会社も、そして国全体も、今や声の響きでつながることができるのです。私の家族を助けたいという願いから生まれた私の発明は、今や全世界の人々がコミュニケーションをとるのを助けることになりました。すべては一つのアイデアと、たくさんの努力、そして少しばかりの好奇心から始まったのです。だから、皆さんに伝えたいことがあります。たとえ他の人が不可能だと言っても、疑問を持つこと、そして何か新しいことに挑戦することを決して恐れないでください。あなたたちのアイデアには、私の「話す電線」がそうであったように、世界を変える力があるのです。
アクティビティ
クイズを受ける
楽しいクイズで学んだことを試してみよう!
色でクリエイティブになろう!
このトピックの塗り絵ページを印刷します。