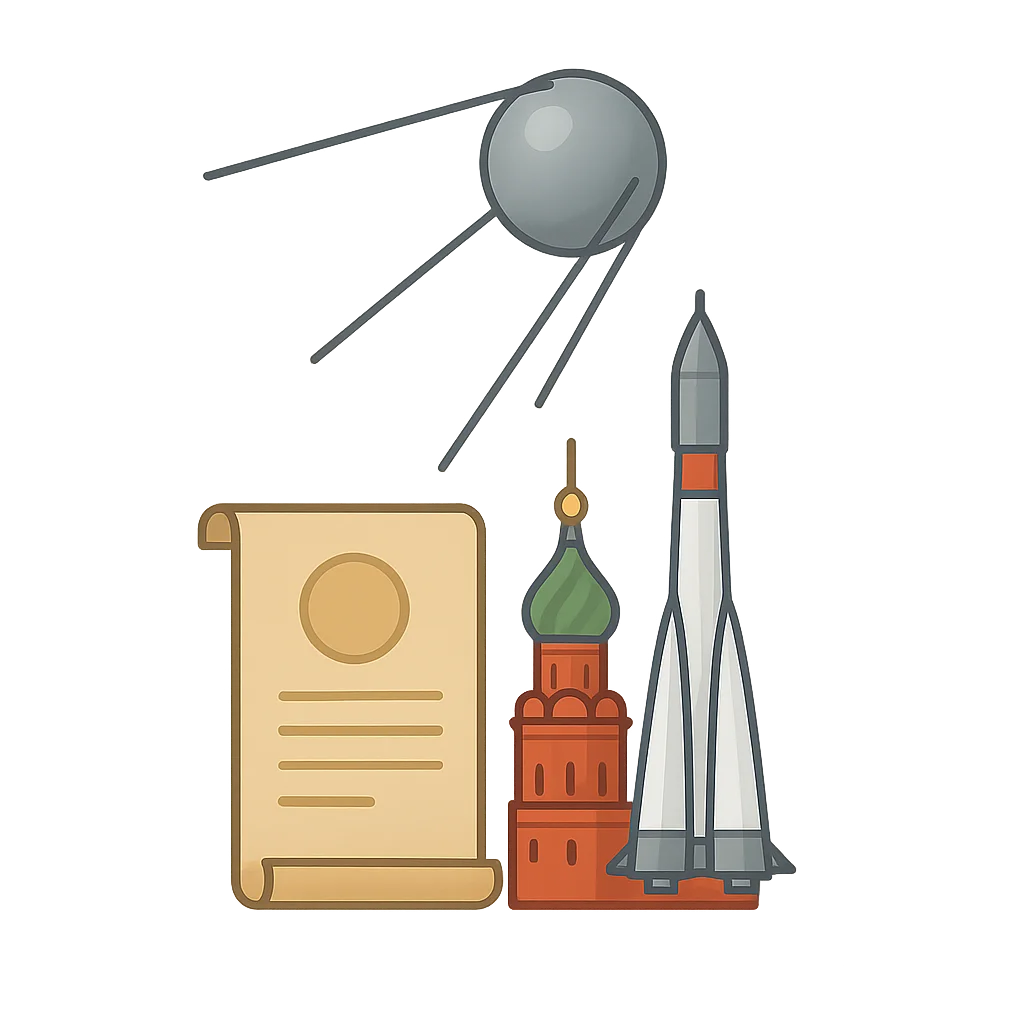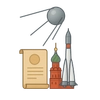チーフデザイナーの夢:スプートニク1号の物語
私の名前を知る者はほとんどいなかった。私のチームの者でさえ、私のことを本名で呼ぶことはなく、ただ「チーフデザイナー」と呼んだ。それは私の秘密の身分だった。しかし、私の心の中には、幼い頃から燃え続ける大きな夢があった。それは、星々の間を旅するという夢だ。まだ少年だった頃、私はコンスタンチン・ツィオルコフスキーという偉大な科学者の本をむさぼるように読んだ。彼は、人類がいつか地球の重力を振り切り、宇宙へと飛び出すだろうと予言していた。その言葉が私の心に火をつけ、私の人生の道を照らす光となったんだ。
1950年代、世界は二つの大きな力、つまり私の国ソビエト連邦とアメリカ合衆国との間で、静かだが激しい競争の真っ只中にあった。人々はこれを「冷戦」と呼んだが、私たちの戦場は地上だけではなかった。それは、遥か頭上に広がる、まだ誰も到達したことのない宇宙空間だった。どちらが先に人類の歴史を塗り替える一歩を踏み出すか。私たちの目標は明確だった。地球の周りを回り続ける、世界初の人工の月、つまり人工衛星を打ち上げることだ。そのためには、これまで誰も作ったことのないような、巨大で強力なロケットを設計し、作り上げなければならなかった。プレッシャーは計り知れないものだったが、私の夢と国の威信が、私たちを前へと突き動かしたんだ。
私たちは、その小さな衛星に愛情を込めて「スプートニク」と名付けた。ロシア語で「旅の仲間」という意味だ。その設計は驚くほどシンプルだった。直径わずか58センチ、ビーチボールほどの大きさの、ピカピカに磨き上げられた金属の球体。そこから、まるで昆虫の触覚のように、4本の長いアンテナが優雅に伸びていた。しかし、この小さな「旅の仲間」を宇宙へと送り届ける任務は、決して簡単なものではなかった。私たちは、そのためにR-7セミョールカという巨大なロケットを開発した。それは当時、世界で最も強力なロケットであり、私たちの希望そのものだった。数え切れないほどの計算、失敗、そして改良を重ね、私たちは来るべき日に備えた。そしてついに、運命の日、1957年10月4日がやってきた。場所はカザフスタンの広大な草原に設けられた、人里離れた発射場だ。発射台に立つR-7ロケットの姿は、まるで天に届かんとする銀色の塔のようだった。地下の管制室の空気は、期待と不安で張り詰めていた。誰もが固唾を飲んで、歴史が動くその瞬間を待っていた。
カウントダウンがゼロになり、点火の合図が出された。次の瞬間、R-7ロケットは雷鳴のような轟音を立て、大地を激しく揺さぶった。オレンジ色の巨大な炎が夜の闇を切り裂き、私たちのロケットは、私たちの夢と希望のすべてを乗せて、星空へと力強く昇っていった。ロケットが夜空の小さな点になり、やがて見えなくなると、管制室には耐え難いほどの静寂が訪れた。成功か、失敗か。スプートニクが無事に地球を回る軌道に乗ったのか、確証を得るまでの数分間は、永遠よりも長く感じられた。誰もがスピーカーに耳を澄ませ、息を殺して待った。その時だ。静寂を破って、スピーカーから微かだがはっきりとした電子音が聞こえてきた。「ピッ…ピッ…ピッ…」。それは、宇宙空間を旅する我々の小さな仲間からの、最初のメッセージだった。その瞬間、管制室は歓喜の爆発に包まれた。私たちは抱き合い、叫び、涙を流した。私たちが成し遂げたんだ。このシンプルで規則正しい信号音は、世界中のアマチュア無線家たちによって受信され、人類が新たな時代、宇宙時代へと足を踏み入れたことを全世界に告げたのだった。
スプートニク1号は、地球の周りを92日間旅した後、その役目を終えて大気圏で燃え尽きた。しかし、その短い旅が残した影響は計り知れない。私たちの成功は、アメリカに大きな衝撃を与え、「宇宙開発競争」の幕開けを告げる号砲となった。この競争が、科学技術を驚異的なスピードで進歩させたんだ。スプートニクという最初の一歩があったからこそ、私たちは次にライカという犬を、そして1961年4月12日には、ユーリイ・ガガーリンという人類初の宇宙飛行士を宇宙へと送り出すことができた。あの夜、私たちが打ち上げたのは、ただの金属の球体ではなかった。それは、人類の未来への扉を開く鍵だったんだ。たった一つの大胆なアイデアと、それを信じ続けた人々の情熱が、新しい世界を切り開くことができる。だから、君たちも夜空を見上げることをやめないでほしい。そして、星の向こうに広がる無限の可能性を、いつまでも夢見続けてほしい。
読解問題
答えを見るにはクリックしてください