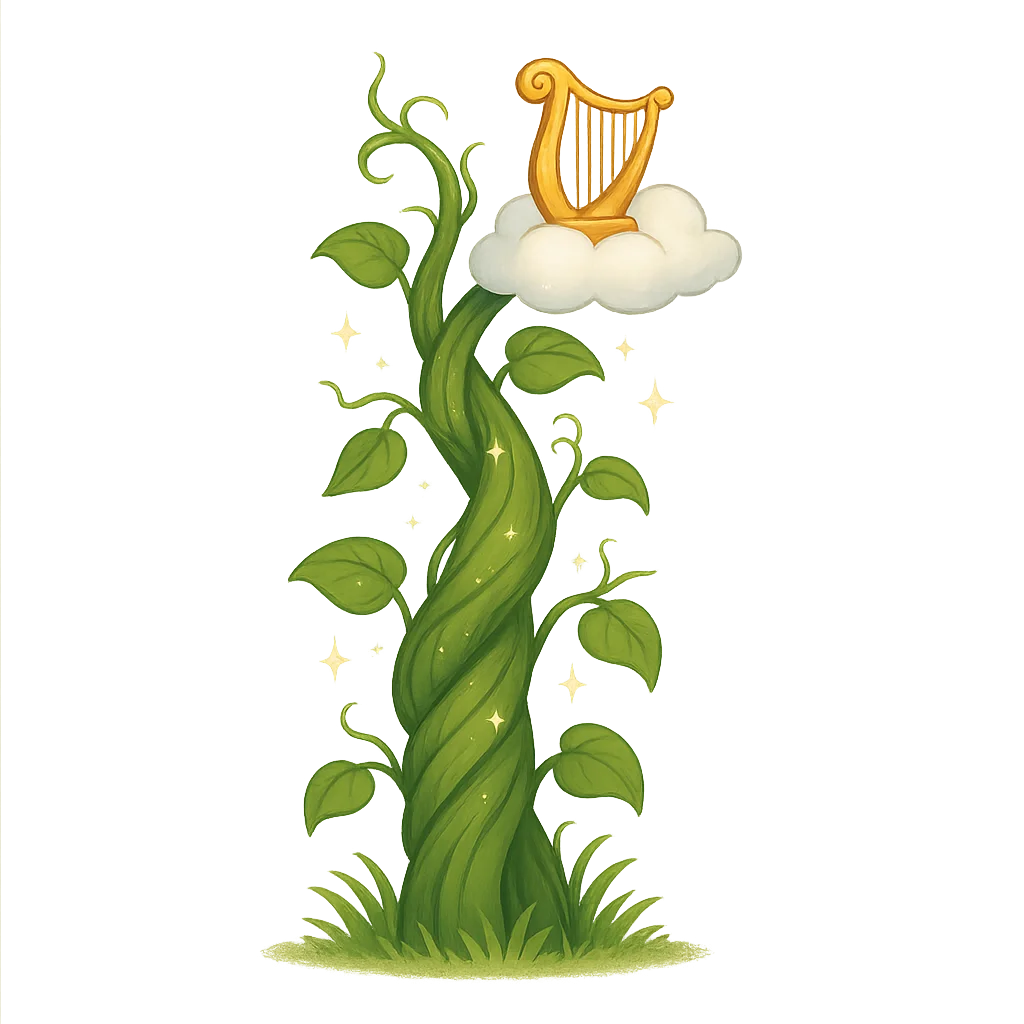ジャックと豆の木
僕の名前はジャック。僕たちの小屋はとても小さくて、外のほこりっぽい道に降る雨の匂いが、そのまま家の中の匂いになるほどだった。母さんと僕に残されたものは、あばら骨が浮き出てきた愛しの乳牛、ミルキーホワイトだけだった。ある朝、母さんは重い心で、ミルキーホワイトを市場へ連れて行くように僕に言ったんだ。でも、世の中は僕に別の計画を用意していた。それは空まで届くほどの計画だった。これは、一握りの豆がすべてを変えてしまった物語、ジャックと豆の木の物語だ。市場へ向かう途中、僕は奇妙な小男に出会った。男は僕に、断れない取引を持ちかけてきた。彼が魔法の豆だと誓う五粒の豆と、僕たちのミルキーホワイトを交換しようと言うんだ。僕の頭は可能性でいっぱいになった――魔法だって!それは僕たちの困難を終わらせるチャンス、天のお告げのように感じた。でも、家に帰ると母さんの顔は曇った。怒りと絶望のあまり、母さんは豆を窓から投げ捨て、僕を夕食抜きで寝室に追いやった。僕は、自分が世界一の馬鹿だと信じながら、お腹を鳴らして眠りについた。
目が覚めると、世界は緑色に染まっていた。毛布ほどもある大きな葉と、僕たちの小屋と同じくらい太い幹を持つ、途方もない豆の木が空に向かって伸び、雲の中へ消えていた。昨夜の愚かさは、驚きと勇気の波に変わった。てっぺんに何があるのか、確かめずにはいられなかった。僕は葉を一枚一枚つかんで登り始めた。下の世界は緑と茶色の小さなまだら模様に縮んでいく。空気は薄く冷たくなったけど、僕は進み続けた。そして、柔らかい白い雲を突き抜けると、そこは別の国だった。まっすぐな長い道が、空そのものを支えているかのように巨大な城へと続いていた。僕は用心深く巨大な扉に近づき、ノックした。すると、木のように背の高い女の巨人、つまり大女が現れた。彼女は驚くほど親切で、僕を哀れに思い、食べ物を少し分けてくれた。でも、彼女は恐ろしい夫の巨人が帰ってくる前に立ち去るようにと警告したんだ。
突然、城が雷のような足音で揺れた。「フィー・ファイ・フォー・ファム、イギリス人の血の匂いがするぞ!」巨人はそう叫びながら部屋にずかずかと入ってきた。大女は僕を急いでオーブンの中に隠した。隠れ場所から、僕は巨人が金貨の袋を数え、やがて眠りに落ちるのを見ていた。チャンスを掴み、僕は金貨の袋を一つひっつかんで、豆の木を急いで下りた。その金貨のおかげで母さんと僕はしばらく食べ物に困らなかったけど、それもすぐになくなった。必要性と冒険心に駆られて、僕は再び豆の木を登った。今度は、隠れて巨人が彼の雌鶏に純金の卵を産むよう命じるのを見た。彼が眠りにつくと、僕はその雌鶏をひょいと抱えて逃げ出した。しかし、三度目は、僕の最後になるところだった。僕は巨人が最も大切にしている宝物を見たんだ。それは、ひとりでに美しい音楽を奏でる小さな金のハープだった。僕がそれを掴んだ瞬間、ハープが「ご主人様、ご主人様!」と叫んだ。巨人はうなり声をあげて目を覚まし、僕を追いかけてきた。僕は逃げた。彼の轟くような足音が、僕の後ろで雲そのものを揺らしていた。
僕は今までになく速く豆の木を駆け下りた。上からは巨人の巨大な手が僕を掴もうと伸びてくる。「母さん、斧を!」地面に足がつくと同時に僕は叫んだ。「早く、斧を!」巨人が下りてくるのを見て、母さんは急いで斧を取りに行った。僕は斧を受け取ると、ありったけの力で振り下ろし、太い幹に切りつけた。何度も何度も切りつけると、やがて大きな音とともに豆の木はぐらりと揺れ、巨人を道連れに倒れていった。地面はその衝撃で揺れ、それが巨人の最期だった。僕たちはもうお金や食べ物の心配をすることはなかった。雌鶏は金の卵を産んでくれ、ハープは僕たちの小さな小屋を音楽で満たしてくれた。僕はただ力だけでなく、機転と勇気で巨人に立ち向かい、勝利したんだ。
何世紀も前にイギリスの暖炉端で語り継がれてきた僕の物語は、ただの冒険譚じゃない。他の人が愚かだと見なすところに機会を見出し、未知の世界に向かって登っていく勇気を持つことについての物語なんだ。それは、どんなに小さな者でも、少しの知恵と大きな勇気さえあれば、最大の困難を乗り越えられることを思い出させてくれる。今日、「ジャックと豆の木」の物語は本や映画、劇の中で成長し続け、人々に大きな夢を抱き、チャンスを掴むよう促している。時には、勇気を出して登ってみることで、最高の宝物が見つかるのだと教えてくれるんだ。
読解問題
答えを見るにはクリックしてください