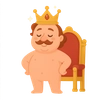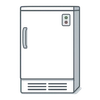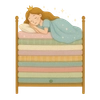お姫様とえんどう豆
うら寂しい夕暮れ時、私の城の小塔の周りを風がうなり声をあげています。これは聞き慣れた音です。私の名はインゲル女王。ここ数ヶ月というもの、私の最大の心配事は息子である王子のことでした。王子は妃を探しに世界中を旅したものの、「本物の」お姫様を見つけることができずに落胆して帰ってきたのです。これは、ある嵐の夜と一つの単純な野菜が、私たち王家の窮地をいかにして救ったかという物語、あなたも「お姫様とえんどう豆」として知っているかもしれません。息子は、称号だけでなく、その存在そのものに気品が備わった、真のお姫様と結婚すると言い張っていました。彼は非の打ち所のない家柄とまばゆいばかりのドレスをまとった数え切れないほどの女性に会いましたが、いつもため息をつきながら帰ってきては、何かが違うと感じていました。「母上、あの方々は本物のお姫様ではありません」と、彼は肩を落として言うのでした。私には彼の言わんとすることが分かりました。真の王族とは、繊細な感受性の問題であり、偽ることのできない生来の資質なのでした。この国の統治者として、私は外見が人を欺くことがあること、そして本物の心はどんな王冠よりも貴重であることを知っていました。私は一つの試練を考案しようと決心しました。それは、最も洗練された感性の持ち主だけが合格できる、非常に巧妙で繊細な試練です。その完璧な候補者が、ずぶ濡れで震えながら、もうすぐ私たちの城門に現れるとは、その時は知る由もありませんでした。
その夜の嵐は猛烈で、城の古い石を揺るがすほどの雷鳴がとどろき、目がくらむほどの土砂降りの雨が降っていました。その混沌の中、正門をノックする音が聞こえました。私の衛兵たちは半信半疑で門を開けると、そこに若い女性が一人で立っていました。髪も服もびしょ濡れで、靴の先からは水が滴り落ちています。彼女は自分がお姫様だと主張しましたが、その姿は嵐に巻き込まれた旅人のようでした。宮廷の人々は疑いの目でささやき合いましたが、私は彼女の疲れた瞳の中に、本物の何かがきらめくのを見ました。私は彼女を温かく迎え入れ、乾いた服と温かい食事を提供しました。その間ずっと、私の計画が頭の中で形作られていきました。「今夜は彼女に快適なベッドを用意してあげましょう」と私は宣言し、自ら客室へ向かい準備をしました。私は召使いたちにマットレスを20枚、そして最高級の羽毛布団を20枚持ってくるように命じました。しかし、彼らがそれらを積み上げ始める前に、私は台所へ行き、小さくて乾いたえんどう豆を一粒持ってきました。そして、それを木製のベッドの土台の真ん中に置いたのです。それから、マットレスと羽毛布団が次々とその上に積み重ねられ、お姫様が登るのに小さなはしごが必要なほど高いベッドが出来上がりました。その土台に隠された秘密を知っているのは、私だけでした。それは感受性を試す究極の試練であり、もし彼女がそれに気づくならば、彼女の王族としての主張が紛れもない真実であることを証明する、あまりにも突飛な挑戦だったのです。
翌朝、私は期待に胸を膨らませながら、朝食の席でお姫様に挨拶をしました。「昨夜はよく眠れましたか、あなた」と、私は声を平静に保とうとしながら尋ねました。彼女は目の下にうっすらと隈ができており、疲れ切った様子でした。「ああ、ひどいものでした!」と彼女はため息をつきながら答えました。「一晩中ほとんど目を閉じることができませんでした。ベッドの中に何があったのかは神様しか分かりませんが、何かとても硬いものの上に寝ていたようで、体中があざだらけです。本当に恐ろしい夜でした!」。私の顔に笑みが広がりました。そして、その話を聞いていた王子は、新たな称賛の目でお姫様を見つめました。私の試練は成功したのです!二十枚のマットレスと二十枚の羽毛布団を通して、たった一粒のえんどう豆を感じることができるのは、それほどまでに柔らかい肌と洗練された知覚を持つ、本物のお姫様だけです。王子は大喜びでした。彼はついに本物のお姫様を見つけたのです。二人はその後すぐに結婚し、そのえんどう豆は王立博物館に収められ、この注目すべき出来事の証として、今日でも見ることができます。この物語は、偉大なデンマークの童話作家ハンス・クリスチャン・アンデルセンが、少年時代に聞いた古い民話に着想を得て、1835年5月8日に初めて書き記したものです。この話は、真の価値は必ずしも外見、つまり豪華な服や立派な称号といった目に見えるものではないことを教えてくれます。時には、感受性や優しさ、誠実さといった最も重要な資質は、心の奥深くに隠されているのです。「お姫様とえんどう豆」の物語は、本や演劇、映画で私たちの想像力を捉え続け、どんなに些細なことでも、その人の人格に関する最も偉大な真実を明らかにすることがあると、私たちに思い起こさせてくれます。
アクティビティ
クイズを受ける
楽しいクイズで学んだことを試してみよう!
色でクリエイティブになろう!
このトピックの塗り絵ページを印刷します。